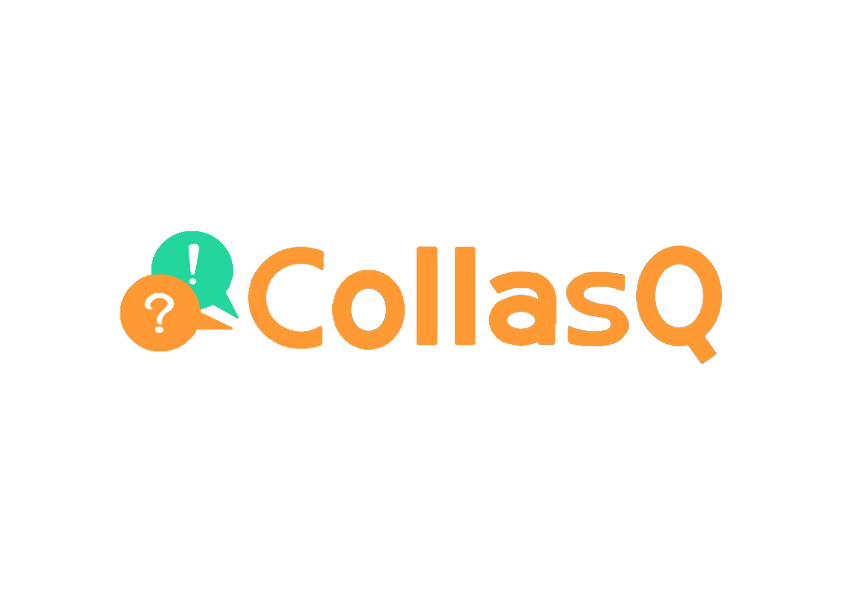チャットボットの導入に失敗しないためには?導入事例や選び方のポイントを解説!

2018年から急激な成長を見せるチャットボット市場。
2018年の市場規模は24億円規模だったのに対し、2022年には市場規模は100億円規模まで拡大すると予想されています。
このように利用者を順調に伸ばしているチャットボットですが、実際にどのように活用されているのでしょうか。
この記事では、チャットボットの導入事例について、業界ごとに詳しく解説していきます。
チャットボットの導入をご検討中の方はぜひ、ご参考にしてください。
チャットボットを導入するメリット
従来のコールセンターのシステムでは、問い合わせ件数が増加するとそれに合わせて対応するオペレーターを用意しなければならずコストも時間も多くかかるものでした。
しかし、チャットボットではあらかじめ問い合わせ事例と回答のルールを設定することで、自動でユーザーの問い合わせに対応することが可能です。
チャットボットをうまく活用することで、オペレーターの負担を大幅に削減可能なため、コールセンターの大きな課題である人材不足の解決策としても注目を集めています。
ここからは、そんなチャットボットの主なメリットについて具体的に解説していきます。
24時間365日対応できる
通常のコールセンターでは平日の日中のみの対応がほとんどで、夜間の対応を行っているコールセンターは多くありません。
しかし、平日の日中は仕事などで、電話をかけられないユーザーがほとんどです。
チャットボットを導入することで、ユーザーは24時間365日いつでも好きな時に、問い合わせが行えるようになります。
また、企業側にとっても日中だけに限定したコールセンターのシステムでは拾いきれなかったユーザーの声を広く集められるため、顧客満足度の向上と共に、顧客離れを防ぐ効果も期待できます。
大量の質問を並行して対応可能
全ての質問に対し、全て人力で対応するとなると顧客を待たせてしまうだけでなく、オペレーターにも大きな負担がかかります。
また、コールセンターにかかってくる質問の多くは、いわゆる「よくある質問」なため、オペレーターにかかる精神的ストレスも非常に大きいでしょう。
チャットボットならば、よくある質問に対し自動で回答を示すことが可能です。
顧客側からすると、素早く問題を解決でき、オペレーターからすれば負担を大幅に削減できるというメリットがあるのです。
また、今まで呼損となっていた可能性のある複雑な質問のみを対応することになるため、サービス改善のヒントを集める場としてもコールセンターを活用できるでしょう。
LINEなどSNS連携でユーザーとの接点を増やせるメリット
また「LINE」や「Facebook」といった馴染みの深いSNSと連携させたチャットボットも増えてきています。
日本国内でのユーザー数が8,000万人以上といわれている今や子供からお年寄りまでに浸透している「LINE」と連携したチャットボットなら、企業の公式サイトにアクセスすることなく、気軽に利用することが可能です。
そのため、今までは質問をする前に諦めていたユーザーとの接点を創造することができるため、顧客満足度のさらなる向上が期待できるでしょう。
企業の業界別導入事例
 チャットボットを導入する業界は多岐に渡っており、コールセンター以外にも、ホテルや飲食店の予約、宅配業者の再配達対応など、業種によってその使われ方もさまざまです。
チャットボットを導入する業界は多岐に渡っており、コールセンター以外にも、ホテルや飲食店の予約、宅配業者の再配達対応など、業種によってその使われ方もさまざまです。
ここからは各業種の具体的な活用事例をご紹介していきます。
飲食業界
飲食業界のチャットボットは主に予約シーンで利用されています。
webからの予約をよりわかりやすく、よりスムーズに行うことが可能になります。
また、店までのアクセスや、前回注文したメニューとは違うメニューをレコメンドする機能や、注文までチャットボットに取らせる飲食店も近年増えてきており、人手不足の打開策として注目を集めています。
金融
制度やその仕組みが複雑になりやすい金融サービスでも、チャットボットが活用され、大幅な人件費削減につながっています。
また、わざわざ電話をかけてオペレーターに聞くよりもチャットを行うほうがはるかにアクションを起こすハードルが低くなるため、商品やサービスを購入するきっかけに大きく貢献しています。
運送業界
運送業界では再配達の自動応答サービスとしてチャットボットが使われています。
従来は配達しているドライバーに直接電話をかけて再配達の申請を行っていたので、ドライバーが運転中でつながりづらかったり、ドライバーも配達の手を止めて応対しなければならず非効率でした。
しかし、チャットボットが一括して受け付けを行うことで、ユーザーはいつでも再配達申請を行うことが可能となり、ドライバーの負担も軽減されています。
通販業界
通販業界では今までも使われてきたFAQの内容をチャットボットに組み込むことによって、ユーザーの疑問が即座に解決できるようになり、利便性が大きく向上するようになりました。
また、商品ページを見て購入を迷っていた層のユーザーがチャットボットで気軽に問い合わせることができるようになり、見込み顧客を逃してしまうことも少なくなりました。
不動産業界
不動産業界では物件探しにチャットボットが使われており、ユーザーは店舗に直接出向くことなく物件を探すことができるようになりました。
また、不動産業界は、不動産投資や不動産登記といった手続きには細かい法律が必要となる場面が多く、対人作業ではその対応者のスキルによってやり取りの進み具合が変わってしまうということが多い業種です。
チャットボットであれば一度ルールを決めてしまえば仕事のムラが出るような心配はありません。
マスコミ・メディア業界
マスコミやメディア業界は、その業界特性からBtoBでやり取りすることが多く、専門的で複雑な問い合わせが多い業種です。
そのため、有人対応を行っていると返信に数日かかってしまうことも少なくありません。
簡単な質問はチャットボットで自動的に、素早く済ませられるようになったことで、浮いた時間を顧客対応に回すことが可能となり、顧客満足度の向上と新規顧客の開拓につなげられています。
チャットボットは社内や自治体でも活用可能!
 チャットボットはコールセンターなどの顧客からの問い合わせに使われるだけでなく、社内の業務ルールの伝達や自治体での住民への説明を行うような場面でも使われるようになってきています。
チャットボットはコールセンターなどの顧客からの問い合わせに使われるだけでなく、社内の業務ルールの伝達や自治体での住民への説明を行うような場面でも使われるようになってきています。
その事例を見ていきましょう。
ヘルプデスク
社内のヘルプデスクのような働きもチャットボットは担っています。
例えばPC接続の不具合や社内ルールの説明といった簡単な質問はチャットボットに回答させることによって、聞く側と答える側双方の負担を軽減することができます。
人によって解決方法が異ってしまうことや、わざわざ出向いて質問するといった無駄を省くことができるため、チャットボットは人件費の削減や、属人化を防ぐ役割も担っているのです。
バックオフィス業務
経理や総務、人事といった直接顧客と対峙することのないバックオフィス業務でもチャットボットは活用されています。
例えば、経理への交通費申請に対する問い合わせの対応や、総務に対する年末調整書類に関する質問など定期的に起こる同じような問い合わせをチャットボットに集約することで、バックオフィス業務の負担軽減を行っています。
地方自治体
民間企業に限らず全国の自治体でもチャットボットは利用されています。
区役所や市役所などで「ごみの分別の説明」や「子育ての質問」といった単純な事柄など膨大な回答ケースがあるものにチャットボットで活用しています。
また「各種証明書発行手続きの方法」や「休日・夜間診療の病院探し」などの質問の多い問い合わせにも対応しており、利用者の満足度向上に大きく貢献しています。
チャットボット導入した企業の失敗事例
さまざまなメリットがあるチャットボットですが万能というわけではなく、機械ならではの弱点もあります。
チャットボットはよくある問い合わせに対して回答することを得意とするシステムですが、その問い合わせ内容や回答事例のルール決めは人間の手で行われます。
その業務範囲を明確にしておかないと、色々なパターンを追求しすぎてシステム実装までに時間がかかってしまうケースは少なくありません。
また、ルール決めがしっかり行えていないと、何度やっても同じ回答を返してしまうケースがあります。
ユーザーがチャットボットを利用する一番の理由は”素早く疑問を解消したいから”です。
結局電話で問い合わせたほうが早かったとユーザーに感じさせてしまうと。かえって顧客満足度が下がる要因となってしまう場合もあります。
チャットボットを有効活用するためのポイントは、ユーザーが求める回答を素早く提供できるようFAQデータを蓄積し、ルールの見直しを定期的に行うことです。
また、自動応対で対応しきれない問い合わせにはスムーズにオペレーター対応に移行できるような流れを組み込んでおくことは必須となります。
事例から学ぶチャットボット導入のポイント
 現在チャットボットは、多くの企業からリリースされており、どのチャットボットを導入するべきか迷ってしまう担当者の方も多いでしょう。
現在チャットボットは、多くの企業からリリースされており、どのチャットボットを導入するべきか迷ってしまう担当者の方も多いでしょう。
ここからは、チャットボット導入に向けて、必ず比較するべきポイントをご紹介していきます。
シナリオ型・AI型か
チャットボットは、大きく分けて2つのタイプに分類することができます。
導入前には必ず、タイプごとの特徴の違いを覚えておきましょう。
シナリオ型
シナリオ型チャットボットは事前に用意されたシナリオに沿い、ユーザーが選択肢を選んでいき規定の回答を返すタイプのチャットボットです。
シナリオ型の最大の利点は導入費用の安さであり、すでにFAQが用意されているような企業に向いています。
AI型
AI型は、1つ質問をしたら1つの回答をするという会話形式のシステムです。
ユーザーからの質問が多岐に渡り、規定の選択肢を用意することが難しい質問が多いサービスでの導入に向いています。
AI型は学習データを取り入れることによって、表記ゆれの認識や回答精度を向上できるのが特徴です。
導入費やランニングコストなど投資対効果を見える化する
チャットボット導入のよくある悩みの1つとして、導入コストが見えづらいということが挙げられます。
チャットボットを利用するには、まず準備段階としてFAQの設問集を作成したり、回答パターンのプログラムを打ち込んだりさまざまな作業を必要とします。
また、サービスを開始してからも対応パターンを増やしたり、回答内容を変更したりするメンテナンスは必須です。
準備とメンテナンスにかかる人的コストをあらかじめ算出しておくことで、システムの予算もうまく調整できるでしょう。
目的に合った使い方ができるか機能の柔軟さをチェック
チャットボットサービスを選ぶ上で機能の柔軟性も重要な要素です。
例えばLINEやFacebookのSNS連携機能が備わっていれば多方面へ露出を増やせるので相乗効果を期待することができます。
また、カスタマイズの追加機能も幅広いシステムなら、さまざまな顧客からの要求に対して臨機応変に対応することが可能です。
チャットボットを導入し何を改善したいのか、目的を明確にして必要な機能を洗い出しましょう。
チャットボット導入なら信頼と実績のあるコラボスへ
チャットボットの導入をご検討中の方はぜひ、コラボスの「Challbo」をご利用ください。
Challboはさまざまな体制に合わせて運用できる管理機能が搭載された新しいチャットボットです。
無人・有人チャットの切り替えなどの必須機能のほかにも、1つのツールで複数のサイトを対応するマルチテナント対応機能、少人数運用に適した複数同時対応機能などが搭載されています。
月額料金3万円からご利用いただけるChallboは、お客様により効果を実感していただけるようにと、導入前の評価が可能な無料トライアルを実施しております。
チャットボットの導入をご検討中の方はぜひ、コラボスまでお問い合わせください。
この記事の執筆者
コラボスブログ編集部
株式会社コラボスは、2001年に設立。現在、東京・大阪にオフィスを構えており、
960拠点以上のお客様へクラウドサービスを使ったCTIシステムを提供。
本ブログ記事サイトでは、様々なニーズを抱えたお客様のお役に立てるような情報を日々発信。
会社情報について詳しくはこちら




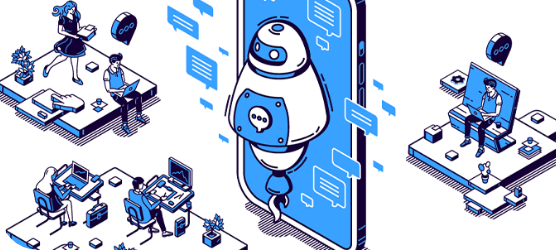

 03-6738-8707
03-6738-8707
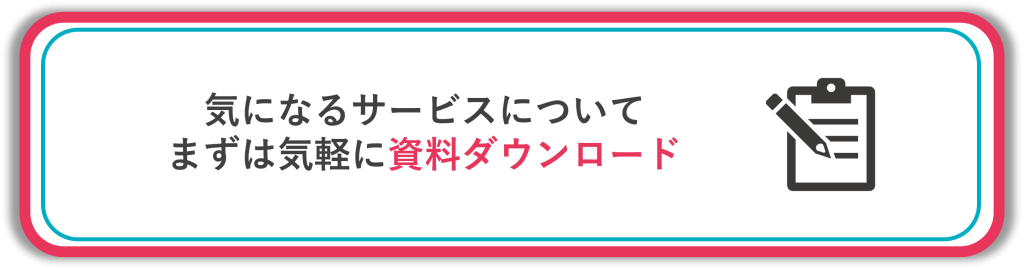
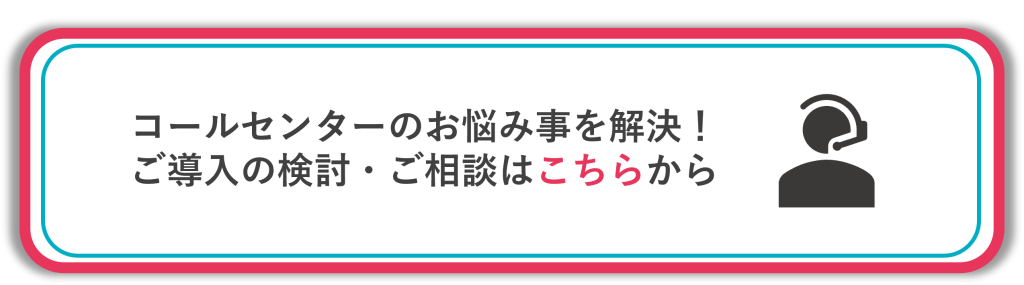



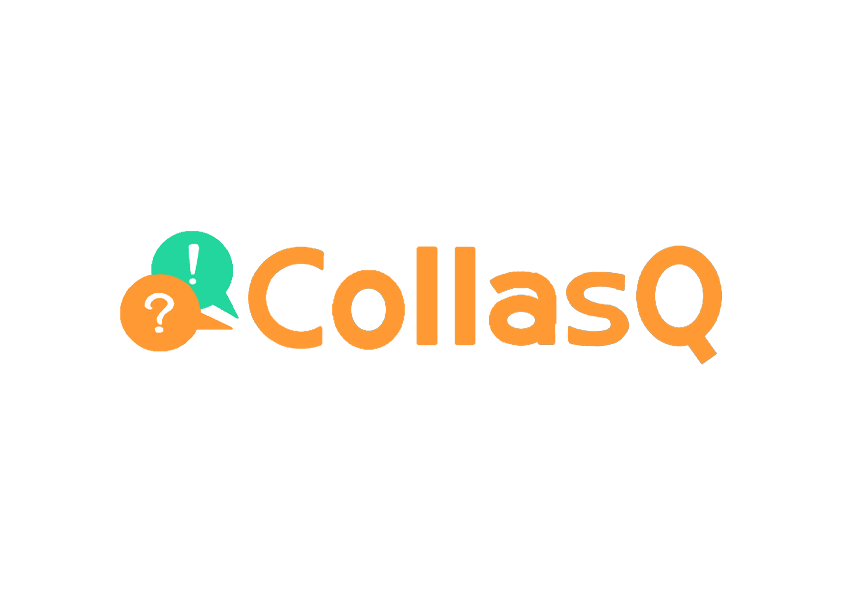




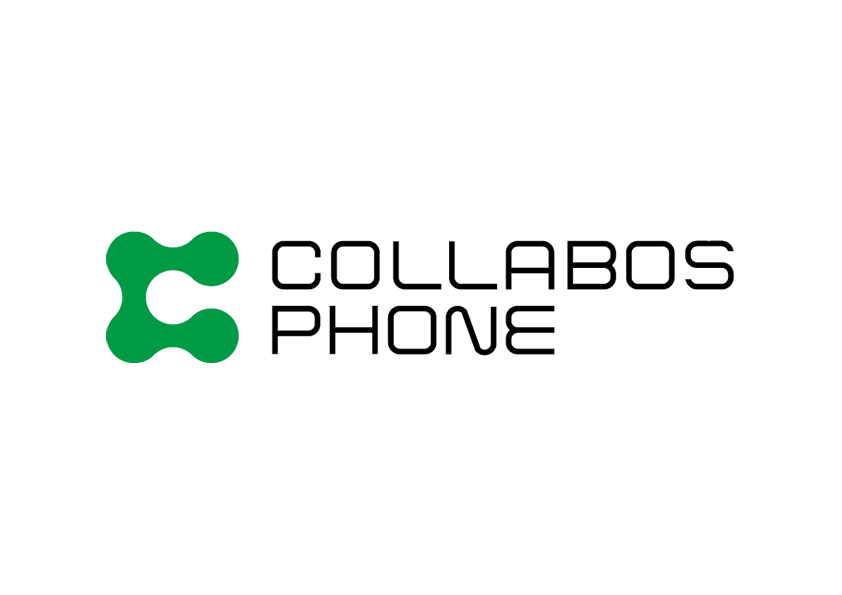



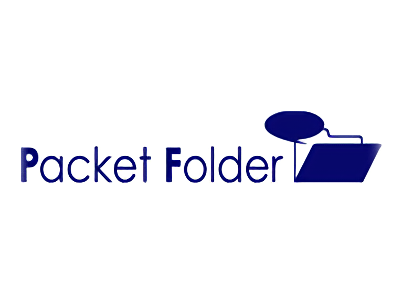


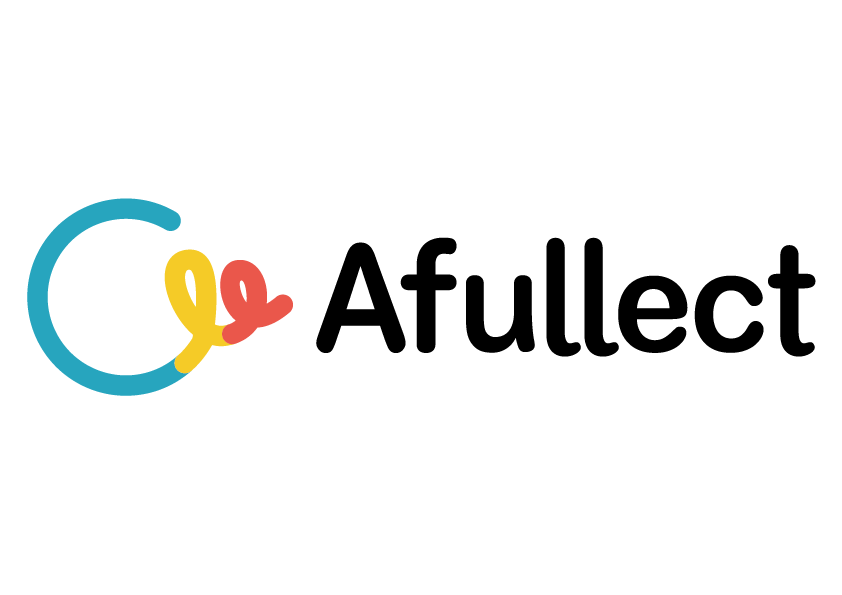
.jpg)