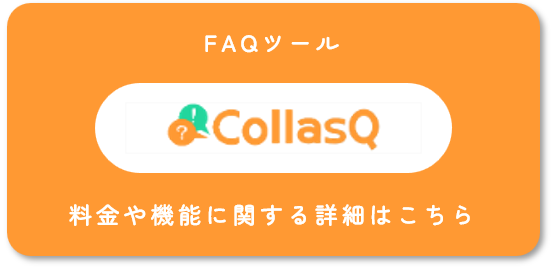2025/12/16
PBX/CTI
顧客情報管理
FAQ
マネジメント
AIでなくなる仕事?コールセンターの現状

近年、コンタクトセンターを取り巻く環境は目まぐるしく進化しています。この流れに乗り遅れると、大きなビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。
この記事では、コンタクトセンターの将来的な展望について詳しく解説しています。
コンタクトセンターやコールセンターを運営されている方は、ぜひご一読ください。
目次
AI時代におけるコールセンターの現状と役割
深刻化する人手不足
コールセンターは「人材の確保」が常に大きな課題です。採用難に加え、研修に手間がかかる一方で離職率も高く、現場では経験豊富な人材が不足しがちです。その結果、応対品質が安定せず、SNSや口コミに悪影響を与えてしまうことも少なくありません。こうした課題を解決するために、AIの導入が注目を集めています。
AI導入の背景
音声認識・自然言語処理・生成AIの進化により、問い合わせの一部は自動化できるようになりました。例えば「営業時間を知りたい」「パスワードを再設定したい」といった定型的な問い合わせはAIが即座に対応可能です。これにより、オペレーターは単純作業から解放され、「人にしかできない複雑な業務」に集中できる環境が整いつつあります。
AI活用がもたらす新しい業務スタイル
チャットボットとボイスボットの進化
従来のチャットボットは「定型文での回答」にとどまっていました。しかし今では自然な会話ができ、簡単なトラブルシューティングにも対応可能です。電話対応におけるボイスボットは、顧客の声をリアルタイムに認識し、適切な回答を提示することで、待ち時間の短縮や応対スピードの向上に貢献しています。
ただし、すべてがAIで解決できるわけではありません。特に感情的なクレームや「ケースごとに判断が必要な相談」では、人間ならではの柔軟な対応が不可欠です。
データ活用による付加価値
AIは膨大な通話ログやチャット履歴を瞬時に分析し、顧客ニーズを可視化できます。
例えば「よくある問い合わせ」を特定してマニュアルを改善したり、顧客ごとに適した対応を提案したりすることが可能です。また、AIによるリアルタイムのデータ分析は、オペレーターへの迅速なフィードバックや、具体的な改善提案を行うことも可能にします。これにより、コールセンターは単なる「対応窓口」ではなく、マーケティングや商品改善にも貢献する「戦略的な拠点」へと進化しています。
-
お客様の生の声を拾い、簡単に傾向分析!:通話録音解析AIツール「UZ」
これからのオペレーターに必要なスキル
専門性と課題解決力
AIが定型業務を担う時代だからこそ、オペレーターにはより高度な知識が求められます。製品・サービスの深い理解や、複雑な問題を解決するスキルが顧客満足度を左右します。単なる「問い合わせ対応」ではなく、課題を分析し提案できる存在が今後の理想像です。
感情をくみ取る力
顧客の怒り、不安、迷いといった「気持ち」に寄り添うことはAIにはできません。たとえば、同じ回答でも「安心させてくれる言い回し」や「気持ちに共感する一言」があるだけで顧客体験は大きく変わります。こうした「人間らしいコミュニケーション」が、オペレーターにしか発揮できない強みです。
デジタルリテラシー
AIを業務で使いこなすスキルも必須です。チャットボットや音声認識ツールを理解し、AIが提示する情報を正しく読み解いて顧客対応に活かす力が求められます。今後は「共感力×デジタル力」を持つオペレーターが、現場のキーパーソンになるでしょう。
AIと人間が共存する「ハイブリッド型モデル」
未来のコールセンターは「AIと人間が協力する仕組み」が基本となります。AIはスピーディで正確な情報提供を担い、人間は感情的な対応や複雑な判断を担当する。こうした役割分担によって、業務効率と顧客満足度を同時に高めることができます。
さらに、AIによる分析結果をマーケティングや商品開発に活用することで、コールセンターは企業全体の成長を支える存在へと進化していきます。
持続可能な成長のために必要なこと
投資と効率化のバランス
AI導入にはコストがかかりますが、単なるコスト削減施策ではなく「顧客体験を高める投資」として考えることが重要です。効率化だけでなく、収集したデータを活かした新しい価値創出が求められます。
人材育成と働き方改革
AIを導入しても「人間オペレーターの価値」はなくなりません。むしろ、複雑な案件に対応するためのスキルや感情対応力を育成する研修が必要です。また、柔軟な働き方やリモート対応を導入し、離職率を改善することも業界の課題解決につながります。
未来のコールセンターを支えるコラボスサービスのご紹介
AIと人間が協力する「ハイブリッド型モデル」を実現するには、現場で無理なく活用できる仕組みが欠かせません。そこで当社では、コールセンターの現場課題を解決する以下のサービスを展開しています。
CTIサービス「VLOOM」
「VLOOM」は、アドバンスト・メディア社の AmiVoice API とGoogleの Gemini を組み合わせた次世代型CTIサービスです。
日々の通話録音からAIが自動でテキスト化・要約を行い、記録や共有の手間を大幅に削減します。また、リアルタイムレポートでオペレーターの状況を把握できるため、管理者が迅速にフォローに入ることが可能。結果的にオペレーターの負担軽減や応対品質の安定につながります。
-
活用例:
新人オペレーターが複雑な問い合わせに対応しているとき、管理者は「VLOOM」のリアルタイムレポートで状況を把握。必要に応じて横からサポートに入れるため、応対の質を守りながら新人育成にも役立ちます。
通話録音解析ツール「UZ」
「UZ」は、通話録音をアップロードするだけでAIが自動的にレポートを作成する解析ツールです。オペレータと顧客との会話内容を解析し、ニーズや興味関心の抽出はもちろん、VOC分析やFAQ生成、広告テキスト作成、オペレータ評価まで幅広く対応します。
-
活用例:
従来、オペレーター教育や評価を行うには、管理者が録音を聞き起こし、応対内容を細かく確認する必要がありました。「UZ」を使えばその作業が不要になります。AIが会話を自動で要約し、応対の流れや改善点をレポート化してくれるため、管理者は短時間で正確に評価が可能。教育に使う教材も自動生成されるので、オペレーターは効率よくスキルアップでき、管理者の負担も大幅に軽減されます。
FAQサービス「CollasQ」
「CollasQ」は、社内・社外の両方で活用できるFAQサービスです。
社内利用:問い合わせ対応のナレッジをデータベース化し、オペレーター教育や対応品質の均一化に役立ちます。
社外利用:蓄積したFAQをサイト上に公開することで、顧客自身が自己解決できるようになり、コール数を削減。コスト低減にもつながります。
さらに、多言語切り替え機能を備えており、外国語での問い合わせにも柔軟に対応可能です。
-
活用例:
よくある操作方法の問い合わせを「CollasQ」にまとめて公開しておくことで、顧客は電話をせずに自己解決。結果的にオペレーターはより高度な案件に集中でき、顧客も待ち時間ゼロで解決できるようになります。
まとめ:AI時代でも、人間オペレーターは欠かせない存在
AIの進化で効率化が進む一方、顧客の気持ちを理解し、信頼を築くのは人間にしかできません。だからこそ、未来のコールセンターは「AIのスピード×人間の温かみ」を両立する場として進化していきます。企業にとっても、このハイブリッド型モデルが競争力のカギとなるでしょう。
この記事の執筆者
コラボスブログ編集部
株式会社コラボスは、2001年に設立。現在、東京・大阪にオフィスを構えており、
960拠点以上のお客様へクラウドサービスを使ったCTIシステムを提供。
本ブログ記事サイトでは、様々なニーズを抱えたお客様のお役に立てるような情報を日々発信。
会社情報について詳しくはこちら