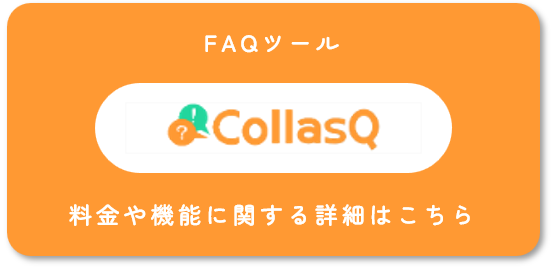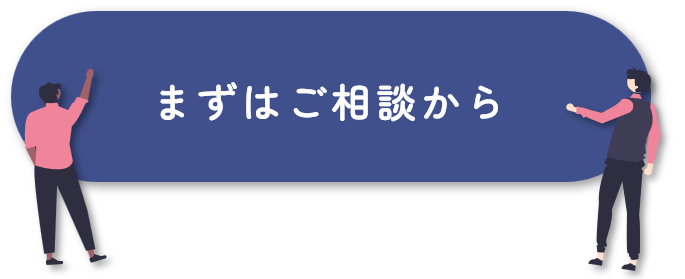2025/07/25
PBX/CTI
通話録音・活用
マネジメント
【徹底解説】コールセンターのカスハラ最新事情と今すぐ始めたい5つの対策

目次
はじめに:コールセンターを取り巻くカスハラの現状
近年、顧客からの過剰な要求や悪質な言動であるカスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題として深刻化しています。特に、コールセンターにおいては、顧客と直接顔を合わせないという特性から、カスハラ被害が顕著に増加しています。
カスハラ(カスタマーハラスメント)とは
カスハラとは、顧客が商品やサービスを提供する企業の従業員に対し、過度な要求や不当な言いがかり、攻撃などを行うことです。
厚生労働省は「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義しています。
コールセンター業界で増加するカスハラ
2022年の日本労働組合総連合会の調査によると、コロナ禍以降に職場でカスハラを受けた人は13.5%に上り、これはパワハラに次いで多い割合です。
顔が見えない電話でのやり取りは、対面よりも攻撃的な言動に繋がりやすい傾向があります。
実店舗の減少に伴い、電話やメールでの問い合わせが増加したことも、コールセンターでのカスハラが増える背景となっています。
社会的注目と企業に求められる対応
カスハラは従業員の心身に大きな影響を与え、企業の生産性低下やイメージ悪化に繋がるため、社会的な注目が高まっており、企業には、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」として、従業員をカスハラから守る責任があります。
東京都では全国初のカスハラ防止条例が制定されるなど、国や自治体も対策に乗り出しており、企業はカスハラ対策への取り組みが急務となっています。
カスハラと正当なクレームの違い
カスハラとクレームは混同されがちですが、その本質は異なります。
クレームは商品やサービスに対する正当な不満や改善要望であり、企業にとって貴重なフィードバックとなり得ます。
一方、カスハラは、要求内容の妥当性を欠くか、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動であり、従業員に精神的・身体的苦痛を与えることを目的とした、またはその結果をもたらす不当な行為です。
カスハラに該当する具体的な行為
カスハラに該当する行為は多岐にわたります。主な具体例としては以下のものが挙げられます。
-
暴言・脅迫
大声で怒鳴る、侮辱する、生命・身体への危害を示唆する発言など
-
執拗な要求・長時間拘束
対応不可能と伝えた内容を繰り返し要求する、意図的に通話を継続し業務を妨害する行為
-
無理難題・不当要求
必要以上の金銭や謝罪、商品交換の要求、法外な賠償やサービスの要求、土下座の強要など
-
従業員個人への攻撃
特定のオペレーターの個人情報を聞き出そうとする、SNSでの誹謗中傷、性的な言動、差別的発言など
クレーム・要望との線引きポイント
カスハラとクレームの線引きは、主に以下の2つの基準で判断されます。
-
顧客等の要求内容に妥当性があるか
商品やサービスに問題がないにもかかわらず過度な要求をする場合、カスハラに該当する可能性があります。
-
要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か
たとえ要求内容が妥当であっても、暴力的・威圧的・継続的・拘束的・差別的・性的な言動は、社会通念上不相当とみなされカスハラに該当します。
これらの基準を参考に、企業ごとに「特定のワードが出たらカスハラ」「何時間以上通話を続けたらカスハラ」といった具体的な判断基準を設けることが重要です。
現場での見極め例
- 正当なクレームの例: 購入した商品に不備があり、謝罪とともに商品の交換を求める。
- カスハラの例: 商品に不備がないのに長時間拘束し返金を迫る。些細な問題で社長の謝罪を要求する。大声で怒鳴りつけたり、執拗に同じ要求を繰り返したりする。
現場の従業員が判断に迷わないよう、マニュアルに具体的な判断基準や事例を記載し、定期的な研修で共有することが効果的です。
コールセンターで実際に起きているカスハラ事例

コールセンターでは、顧客との電話対応という特性上、対面では発生しにくい、またはエスカレートしやすいカスハラが多く報告されています。
暴言・人格否定・威圧的言動
- 「お前には理解できないのか」「上司を出せ」「お前のようなバカでは話にならないから上司を出せ」など、オペレーターの人格や能力を否定する発言。
- 「お前の名前と社員番号を言え」「このやり取りは全て録音している。訴えてやる」などの威圧的な要求。
- 「死ね」「クズ」といった過激な暴言や、「殺すぞ」「今からそこに行くぞ」といった脅迫的な発言。
- 「お前は向いていない。やめろ」「まだやめていないのか」といった特定オペレーターへの執拗な個人攻撃。
執拗な電話や長時間拘束
- システム仕様上対応が不可能な内容に対して、「できない理由を具体的に説明しろ」と長時間の通話を続けさせる状況。
- 企業に重大な過失がない場合でも、理不尽な要求を長時間にわたり強要する。
- 同じ内容のクレーム電話を繰り返し執拗にかける行為。
無理難題・不当要求
- 軽微なミスに対し、社長の謝罪や土下座を要求。
- 問い合わせに対して法外な補償や金銭的見返りを無理に求める。
- 商品の欠損がないにもかかわらず、高額な返金を強要。
- サービス解約手続き中に感情的になり、不合理な賠償請求を行う。
これらの事例は、コールセンターで働く従業員が受ける精神的負担の大きさを浮き彫りにしています。企業全体で徹底した対応策を講じることが、従業員保護と健全な業務運営のために不可欠です。
コールセンターでは、電話越しのコミュニケーションという特性上、対面では発生しにくい、あるいはエスカレートしやすいカスハラの事例が多く報告されています。
カスハラがもたらすリスクと課題
コールセンターにおけるカスハラは、単なる迷惑行為にとどまらず、従業員の心身、企業の運営、そして法的側面において深刻なリスクと課題をもたらします。
従業員の心身への影響
カスハラは、対応するオペレーターの心身に多大なストレスと悪影響を与えます。
- 業務へのモチベーション低下: カスハラを経験することで、通常の問い合わせ対応にも消極的になりがちです。
- 通常の応対に対する不安や恐怖: 次はいつ同じような事態に遭遇するかという不安を抱えながらの業務となり、過度な緊張や不安により、本来の能力を発揮できなくなります。
- ストレス蓄積による休職や離職: 継続的なカスハラにより、精神的な負担が蓄積し、最終的に休職や離職に追い込まれるケースも少なくありません。特に電話での対応は相手の表情が見えない分、精神的負担が大きくなりやすいです。
運営側(管理職・企業)に与えるリスク
カスハラは、オペレーター個人だけでなく、コールセンター運営や企業全体にも悪影響を及ぼします。
- 業務生産性の低下: 長時間のカスハラ対応は、他の顧客への対応の遅れや本来の業務への支障を招きます。対応件数の低下や残業の増加など、コールセンター全体の生産性が著しく低下します。
- 他の顧客対応の品質低下: カスハラ対応に時間を取られることで、他の顧客への対応が手薄になり、全体的なサービス品質が低下する可能性があります。
- 職場全体の士気低下: 同僚がカスハラを受ける様子を見ることで、チーム全体のモチベーションが下がり、職場の雰囲気が悪化します。
- 人材採用・定着率への悪影響: カスハラの多い職場として認識されると、新規採用が困難になり、既存スタッフの離職も増加し、人材不足が深刻化する可能性があります。
想定される訴訟や法的トラブル
企業がカスハラ対策を怠った場合、法的責任を問われるリスクがあります。
- 安全配慮義務違反: 企業には労働契約法第5条に基づき、従業員の生命、身体の安全を確保しつつ労働できるような必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。カスハラに対して適切な対応を行わない結果、従業員が心身の不調をきたした場合、企業は安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求される可能性があります。実際に、カスタマーハラスメントが原因で従業員が企業を訴え、損害賠償が認められた事例も存在します。
- 企業イメージの低下と損害賠償: カスハラがSNSなどで拡散されれば、事実とは異なる悪評が定着し、企業のイメージが大きく損なわれる可能性があります。これにより売上減少や株価下落など、経済的な損失に繋がることもあります。悪質なカスハラ行為自体が脅迫罪、恐喝罪、強要罪、威力業務妨害罪、不退去罪などの刑法上の罪に該当する場合もあり、警察への通報や法的措置が必要となることもあります。
これらのリスクを回避し、従業員を守りながら健全な事業運営を続けるためには、効果的なカスハラ対策の整備が不可欠です。
コールセンターのためのカスハラ対策5選

コールセンターでカスハラから従業員を守り、健全な業務運営を維持するためには、体系的な対策が必要です。ここでは、特に重要な5つの対策を紹介します。
1. 専用対応マニュアルの整備と従業員教育
カスハラに対する認識を統一し、具体的な対応を標準化するために、専用のマニュアルを作成し、従業員教育を徹底することが不可欠です。
- カスハラの定義と判断基準の明確化
自社にとって何がカスハラに当たるのかを具体的に定義します。厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、日本コンタクトセンター協会が公開しているガイドラインなどを参考に、「特定のワードが出たらカスハラ」「何時間以上通話を続けたらカスハラ」といった具体的な基準を設定します。 - 対応フローの明文化
カスハラが発生した際の初動対応から、管理職や人事部へのエスカレーション、警察・弁護士への連携までの一連の流れを明確にします。例えば、「暴言や罵声が20分以上続く場合は電話を切る」「正当な理由なく無理難題を要求されたら上長に電話を代わってもらう」といった具体的な指示を盛り込みます。 - 実践的な研修の実施
マニュアルに基づいたロールプレイングやケーススタディを定期的に行い、従業員が自信を持って対応できるようスキルを向上させます。特に、クレームとカスハラの見極め方、毅然とした態度での断り方、自身の安全を確保する方法などを重点的に教育します。管理職や相談担当者にも、対応方法や従業員ケアに関する研修を行います。
2. CTI・音声認識システムなどのテクノロジー活用
テクノロジーを導入することで、カスハラの検知、対応、分析を効率化し、オペレーターの負担を軽減できます。
- リアルタイム音声テキスト化
顧客との会話をリアルタイムでテキスト化することで、スーパーバイザー(SV)が通話内容を効率的にモニタリングし、カスハラの兆候を早期に検知できます。 - 要注意ワードのアラート通知
事前に登録した暴言や脅迫的なワードが発言された場合に、管理者にアラートを通知する機能を活用することで、深刻な事態になる前にSVが介入しやすくなります。 - 感情認識機能
AIによる感情分析機能は、顧客の感情の動きを可視化し、オペレーターが対応を調整するのに役立ちます。また、管理者も顧客の感情の高ぶりをリアルタイムで把握し、適切なタイミングでサポートに入ることが可能になります。 - 自動要約機能
通話内容をAIが自動で要約することで、後処理の時間を短縮し、オペレーターの負担を軽減します。また、カスハラ事案の記録管理も効率化できます。 - IVR(自動音声応答システム)の活用
「この通話は品質向上のため録音させていただきます」といった自動アナウンスを流すことで、不適切な言動を抑制する効果が期待できます。また、緊急度に応じた適切な部署への振り分けや、クレーム内容を自動音声で受け付けて後から折り返し連絡する運用も、感情的な即時対応のリスクを軽減します。
3. 通話録音や音声ガイダンスの導入
通話録音と事前告知は、カスハラ行為の抑止力となり、万が一の際の証拠保全にも役立ちます。
- 通話録音の徹底
すべての通話を録音し、カスハラ被害の明確な証拠として残します。録音データは、相手の怒りの原因分析や、法的措置を検討する際の重要な資料となります。 - 録音している旨の事前告知
通話開始時に自動音声で「この通話は迷惑電話防止や品質向上を目的に録音されています」とアナウンスすることで、悪質な言動を未然に防ぐ効果が期待できます。これにより、顧客側が言葉を選んで話すようになるケースもあります。 - 毅然とした対応への活用
録音していることを伝えることで、オペレーターが毅然とした態度で対応しやすくなります。不当な要求や暴言が続く場合に「録音していることを踏まえて、これ以上の対応はできかねます」と伝えることで、状況が改善されることもあります。
4. 社内外のサポート体制・相談窓口の確立
オペレーターが一人でカスハラ問題を抱え込まないよう、複数の階層でサポートできる体制を整えます。
- 社内相談窓口の設置
カスハラを受けた従業員が速やかに相談できる専門窓口を設置します。相談内容の秘密保持を徹底し、従業員が安心して利用できる環境を整備します。 - エスカレーション基準の明確化
どのような言動があった場合に上位者(SVや管理職)に引き継ぐのか、具体的な基準を設けます。「同じ要求を3回以上繰り返す」「通話時間が一定時間(例:15分)を超える」など、数値基準を設定することでオペレーターの判断負担を軽減します。 - 複数人での対応体制
一人のオペレーターに負担が集中しないよう、状況に応じてSVや同僚がサポートに入れる体制を構築します。リアルタイムモニタリングや、オペレーターが「助けを求めるサイン」を出せる仕組み(チャットツールの活用や非常ボタンの設置など)を確立し、即座にバックアップに入れる体制を作ることが重要です。 - メンタルヘルスケアの提供
カスハラ対応後の従業員の精神的なケアも重要です。定期的なストレスチェックや面談、産業医やカウンセラーによるサポートなど、心のケアを徹底します。 - 外部専門機関との連携
弁護士や警察、労働組合、保険会社など、社外の専門機関と連携できる体制を整えます。明らかな違法行為があった場合の法的措置の基準を設定し、躊躇なく対応できるよう準備します。
5. 顧客へのカスハラ抑止告知・ルール周知
カスハラ行為を未然に防ぐため、企業としての姿勢を顧客へ明確に伝え、一定のルールを周知することも有効です。
- 企業HPやサービスページでの方針明記
企業のウェブサイトやサービス利用規約などに、カスハラに対する基本方針を明確に記載します。「従業員を守るためにカスハラを許さない」という姿勢を外部に示し、具体的なカスハラ行為の例や、それに対する企業の対処法(例:サービス提供の停止、警察への通報など)を明記します。 - 駅構内や店舗でのポスター掲示
鉄道会社が駅構内にカスハラに関するポスターを掲示しているように、顧客接点のある場所でカスハラ抑止を訴えるメッセージを発信します。厚生労働省も啓発ポスターを配布しており、これを活用するのも良いでしょう。 - 契約プランやWebサイトのシンプル化
顧客の誤解や不満がカスハラに繋がらないよう、契約プランやウェブサイトの情報を分かりやすくシンプルに設計します。特に解約や変更手続きは、顧客がスムーズに行えるよう配慮することで、無用なトラブルを減らせます。 - 「3つのカエル」の意識
顧客の怒りが興奮状態にある場合、「人」「時間」「場所」を変えることで落ち着く傾向があるという「3つのカエル」を意識した対応を組織全体で共有します。コールセンターでは、対応オペレーターの交代や、一旦電話を切って責任者からかけ直すなどの「時間」を置く対応が有効です。
これらの対策を継続的に実施し、定期的に見直すことで、コールセンターは従業員を守り、顧客との良好な関係を築きながら、より良いサービスを提供できるようになります。
ケース別対応フロー策定のすすめ
具体的なカスハラ行為の類型ごとに、現場での対応フローを策定し、マニュアル化することが不可欠です。
- 長時間拘束型:
- 通常のクレーム対応を試みる(傾聴、共感、解決策の提案)。
- 一定時間(例: 20分)を超過した場合、対応できない理由を明確に伝え、電話を切る旨を告知する。
- 解決策の提示後も膠着状態が続く場合、「後ほどかけ直す」と伝えて一度電話を切る。
- オペレーターを交代し、冷静に対応できる別の担当者が引き継ぐ。
- 暴言・人格否定型:
- 暴言をやめるよう毅然と求める。
- 侮辱的発言や名誉毀損、人格を否定する発言があった場合、後で事実確認ができるよう通話を録音する。
- 程度がひどい場合は、上司にエスカレーションし、必要に応じて法的措置を検討する旨を伝える。
- 脅迫・威嚇型:
- 複数人で対応し、対応者の安全確保を最優先にする。
- 「このような発言が続く場合は通話を終了させていただく」旨を毅然と伝える。
- 生命・身体への危害を示唆する発言があった場合、躊躇なく警察への通報を検討する。録音データも証拠として活用する。
- 執拗な個人攻撃型:
- 特定の個人への中傷や個人情報の要求には応じられない旨を明確に伝える。
- 必要に応じて通報対象となることを説明する。
- 該当するオペレーターを保護するため、当面の間は該当顧客との対応から外す措置を検討する。
これらのフローは、従業員が一人で問題を抱え込まず、組織として連携して対応できるような仕組みにすることが重要です。
コールセンター現場で今すぐできる実践アクション

コールセンターの現場でカスハラ対策を効果的に進めるためには、具体的なシステムやツールの導入、そしてそれらを活用した対応フローの策定が重要です。
システム・ツール選定のポイント
カスハラ対策に有効なシステムやツールを選定する際には、以下のポイントを考慮しましょう。
- 通話録音機能
すべての通話を自動的に録音し、容易に検索・再生・ダウンロードできるシステムが望ましいです。通話開始時に自動音声で録音している旨をアナウンスできる機能も重要です。これにより、カスハラ行為の抑止と証拠保全を同時に行えます。 - CTI(Computer Telephony Integration)システム
顧客情報や過去の対応履歴を瞬時に表示できるCTIシステムは、オペレーターが顧客の背景を素早く把握し、適切な対応をとる上で役立ちます。特定の顧客からの繰り返し連絡や悪質なクレーム履歴も共有できます。 - 音声認識・感情解析システム
リアルタイムで会話をテキスト化し、特定のキーワード(例:暴言、脅迫)や感情のトーン(例:怒り、威圧)を検知してアラートを出す機能は、SVのモニタリングを効率化し、深刻な事態になる前に介入を促します。 - IVR(Interactive Voice Response)システム
自動音声応答により、顧客の問い合わせ内容に応じて適切な部署に振り分けたり、FAQへの誘導を行ったりすることで、オペレーターへの負担を軽減します。迷惑電話を自動で切断する機能も設定可能です。 - ナレッジマネジメントシステム(FAQシステム)
よくある質問とその回答を体系的にまとめることで、顧客の自己解決を促し、コールセンターへの問い合わせ件数を削減します。オペレーターも迅速に正確な情報を提供できるようになり、対応品質の向上に繋がります。
カスハラ対策のシステムはコラボスでまるっと解決!
サービスの詳細はこちらから!
現在の課題感や、コールセンターの方針によって、システムの合う/合わないがあると思います。
「ツールが多く、何から始めればいいのかわからない・・」というお客様もぜひお気軽にご相談ください。
現状の課題感をヒアリングさせていただき、貴社のご運用に合わせたご提案をさせていただきます!
最新ガイドライン・法的枠組みと行政の動向
カスハラへの対策は、企業にとって重要な経営課題として認識されており、国や地方自治体もその対策を強化するための法的枠組みやガイドラインを策定しています。
厚生労働省のカスハラ対策指針
厚生労働省は、2020年1月に「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(いわゆる「パワハラ指針」)を策定しました。この指針では、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスハラ)に関して、事業主は以下の措置を講じることが望ましいとされています。
- 相談に応じ、適切に対応するための体制整備
- 被害者への配慮の取り組み
- 被害を防止するための取り組み
さらに、2022年2月には「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、カスハラの判断基準や企業の具体的な取り組み、そのメリットなどについて詳細に解説しています。このマニュアルは法的な効力を持つものではありませんが、企業のカスハラ対策を推進する上での重要な指針となっています。
労働契約法・労働施策総合推進法などの関連法規
企業は、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」を負っています。これは、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務です。カスハラによる従業員の心身の健康被害を防ぐことは、この安全配慮義務に含まれます。
また、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)は、職場におけるパワハラ防止措置を事業主に義務付けていますが、この法律の指針の中でもカスハラへの対応が言及されています。カスハラ行為が悪質な場合は、刑法上の暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪、業務妨害罪、不退去罪などに問われる可能性もあります。
まとめと今後の展望
カスハラ対策の重要性と早期着手のメリット
コールセンターにおけるカスタマーハラスメントは、オペレーターの心身の健康を著しく損ない、企業の生産性低下、離職率の増加、さらには企業イメージの悪化や法的リスクに直結する深刻な社会問題です。企業には労働契約法に基づく安全配慮義務があり、従業員をカスハラから守ることは企業の社会的責任でもあります。早期にカスハラ対策に着手することで、これらのリスクを最小限に抑え、従業員が安心して働ける環境を整備できます。
従業員を守り、顧客との良好な関係を築くために
カスハラ対策は、単に迷惑行為を排除するだけでなく、従業員を守り、ひいては顧客との良好な関係を再構築するための基盤となります。明確なカスハラの定義、詳細な対応マニュアルの整備、定期的な従業員研修、そして通話録音やAIを活用したシステム導入など、多角的なアプローチが求められます。特に、テクノロジーの活用は、カスハラの早期検知、効率的な対応、そしてオペレーターの心理的負担軽減に大きく貢献します。また、カスハラに対する企業の毅然とした姿勢を内外に明確にすることで、健全な顧客関係を築くことができます。