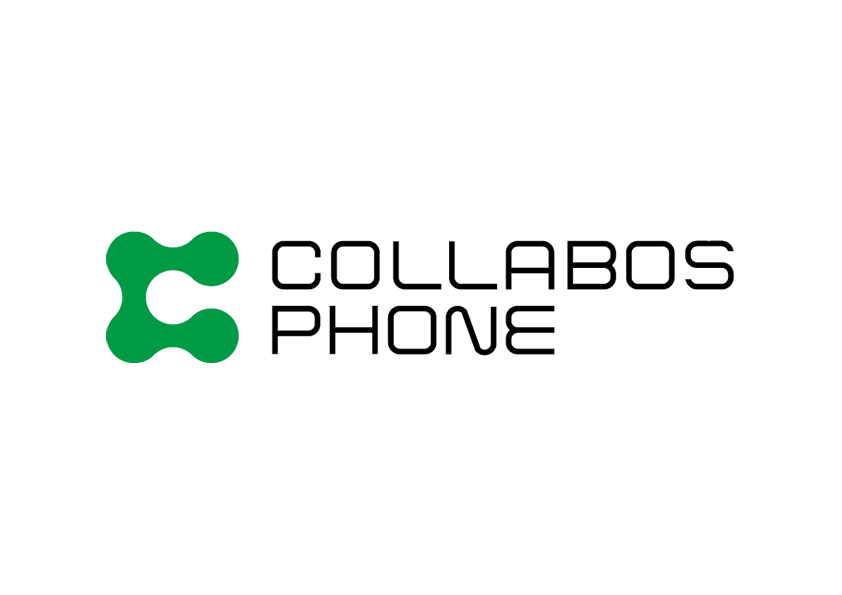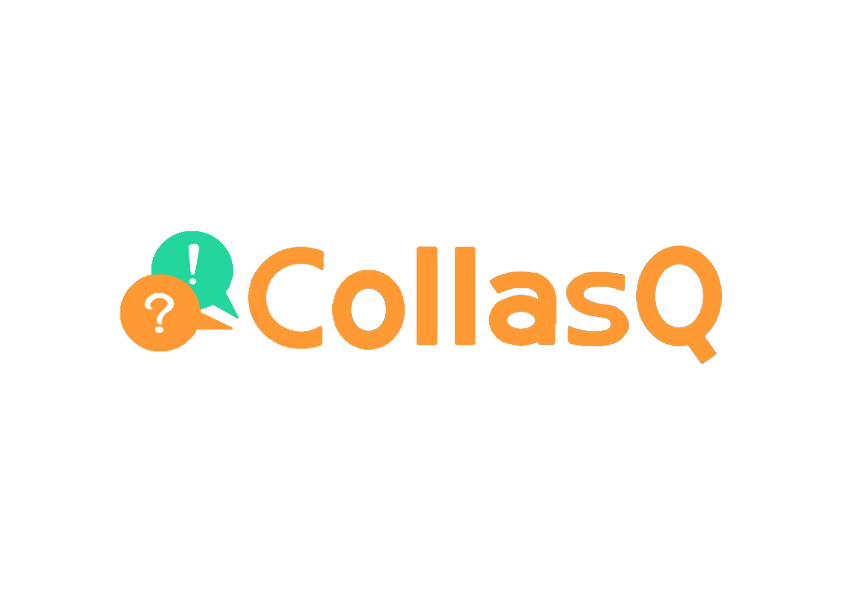コールセンターのSV(スーパーバイザー)とは?業務内容や育成のコツを解説

コールセンターを運営していくには、システム、人材、管理方法など様々な部分で課題や検討しなければならない事項があります。ここではコールセンターを運営していく基本的な方法や、認識すべき課題、SV(スーパーバイザー)はどのような仕事をしなけばいけないのかなど、コールセンターの運営について様々な確度で紹介していきます。
そもそもSVとは?
そもそも、SVとは何の略なのでしょうか。SVとは「スーパーバイザー」の略です。コールセンターにはオペレータとSVが基本的に常駐しており、オペレータの育成やサポート担当をする人をSVと呼びます。
コールセンター(コンタクトセンター)運営で実施すべきこと
ではコンタクトセンターおよびコールセンターを運営していくうえで実施しなければいけないことにはどのようなことがあるのでしょうか。
課題を明確化する
1つ目は課題を明確化することです。自社のコールセンターにはどのような課題があるのか、達成できていない目標や解決できていない問題がどこにあり何が原因なのかを明確化し、より効果的に課題を解決できる手段を検討していく必要があります。
運営の目的を明確にする
コンタクトセンターやコールセンターはコストセンターと呼ばれてしまうことも多いため、センターを運営する目的を明確化する必要があります。ただ漠然とお客様の問い合わせ先として設けるのではなく、どのように売り上げにつなげていくか、顧客満足度を向上させるかなどを検討していく必要があります。
日々の業務の評価をする
3つ目は日々の業務を評価するということです。センターで掲げている目標達成に向けて順調に向かっているかどうかを確認するためにも、パフォーマンスや品質などを定期的に評価することで、運用を円滑に進めていく必要があります。評価することで新たな課題の発見にもつながる可能性があります。
コールセンター(コンタクトセンター)のSV(スーパーバイザー)の仕事内容・役割
コールセンターのSV(スーパーバイザー)は、オペレーターを管理・統括しています。
オペレーターを経験し、業務知識・スキルを磨いたリーダーがSV(スーパーバイザー)として業務にあたります。
ここではSV(スーパーバイザー)の仕事内容・役割がどのようなものなのか詳しくご紹介していきます。
コールセンター業務管理
コールセンターにおけるSVの業務内容は多岐に渡ります。
SVには以下のようなコールセンター業務全体を把握すると同時に、さらに他部署との連携を図る役割があります。
- 朝礼・終礼・ミーティングなど日々の定例業務
- 個々のオペレーターのコール品質管理
- オペレーターのエスカレーション受け入れ
- 呼量による人員配置の策定と実施
- センター全体における生産性管理・向上
- 業務改善の案と実施
- 他の部署や管理部門との連携
SVはコールセンター運営業務を網羅的に把握し、オペレーターがスムーズに業務にあたれるようサポートしています。
クレームや難易度の高い問い合わせへの対応
顧客がその商品やサービスの購入を真剣に検討している場合、コールセンターには難易度の高い問い合わせが入電します。
しかし、問い合わせが解決できなかった場合、顧客の不満へつながり、さらに不手際があった場合はクレームに発展する恐れがあります。
なぜなら顧客は商品やサービスに期待をしているからです。
もちろんオペレーターはフロント対応で何とか顧客の疑問や不満を解決しようと対応にあたりますが、全ての顧客の期待を上回ることは難しく、オペレータースキルによってはさらなる不満やクレームを招いてしまう結果が多々あります。
そのような場合、SVはエスカレーション先として対応を交代し、顧客の不満やクレームを満足へ変える役割を担います。
この交代による顧客への対応は重要で、今後、顧客がその企業を信頼し購買行動を行うかどうかはSVにかかっているともいえるため、慎重な対応が求められます。
オペレーターの研修
コールセンターではオペレーターのスキル品質を確保するため、研修制度が設けられています。
オペレーターは企業の顔ですが、顧客とは通話やメールなどだけでサービスや商品のやりとりを行います。
顔が見えない分、声色、発声、発話、コミュニケーション力などが必須となり、同じサービスの案内でも、スキルによって顧客の購買行動に影響が出てしまいます。
そのため、品質を一定以上に引き上げるために次のような研修でオペレーターをサポートしていきます。
- 応対品質研修
- 業務内容研修
- OJT研修
オペレーターには独り立ちまでに充分な事前研修を行い、独り立ち後も品質チェックや随時研修を行い、品質を保っていきます。
コールセンターの労働環境の改善
コールセンターの離職率を下げるためには、労働環境の改善が必須です。
例えばコールセンターを離職する理由として次のようなものが挙げられます。
- 覚えることが多い
- 長時間労働が辛い
- 低賃金
- 顧客の無理難題やクレーム対応に疲弊
- 孤独な作業を毎日繰り返す
- 職場の人間関係が悪い
これらの不満を解消するべく、SVは改善を行う必要があります。
コールセンターSVの給料・平均年収
コールセンターSV(スーパーバイザー)の平均年収は約422万円です。月給に換算すると約35万円程度です。
派遣社員やアルバイト・パートの場合、平均時給はそれぞれ1,438円と1,299円となっています。
地域別に見ると、最も高いのは東京都で、平均年収は466万円です。なお、これはあくまで一例で、地域や勤務先、経験、スキルによって大きな差が生じることがあります。
コールセンターSVの主な業務には、オペレーターの研修や育成、シフト管理、品質管理、進捗管理、クライアント対応などが含まれます。リーダーシップやコミュニケーション能力が求められる職種であり、責任も大きい重要な職種です。
コールセンターSVのやりがい
メンバーの成長が励みになる
これまで成長に課題を抱えていたオペレーターが成長し、成果を挙げるようになると、目標達成以上の喜びを感じることができるかもしれません。さらに、様々な改善や業務の工夫を通じてチーム全体がコミュニケーションを密にし、人間関係が円滑になり、士気が高まると、チームの育成業務もより楽しくなるでしょう。
責任が重いため、目標達成時の喜びもひとしお
SVには目標数値の達成に対する責任があり、そのため個々のオペレーターよりもプレッシャーを感じることが多いです。しかし、責任の重みに見合った成果が上がれば、大きな達成感を得ることができます。クライアントからの感謝の言葉も得られるかもしれません。これは励みになり、仕事へのモチベーションも一段と高まるでしょう。
仕事の幅が増える
クライアントとの対話を通じて、「このコールセンターをどう進化させたいか」「クライアントや自社にどう貢献したいか」といった考えに基づいて施策を立案し、さまざまな局面で最終的な判断を下す機会が増えます。
仕事の範囲や責任の重みには時に圧倒されることもありますが、それが大きなやりがいとなるかもしれません。
コールセンターSVに求められるスキル
SVにはバランスのよい人物が求められます。
業務スキルを一通り習得し、フロントオペレーターでは対応が困難な顧客の問い合わせやクレームの解決、他部署との連携まで幅広いスキルと視野が必要です。
ここでは、SVとして働くために求められるスキルにはどのようなものがあるのか、ご紹介していきます。
広い視野で行動をする力
SVはセンター全体の業務を定量的に把握し、広い視野を持って行動することが必要です。
自身の業務を行いながら、平行して対応に苦慮しているオペレーターを見つけ迅速に対応したり、指示を出したりしなければなりません。
並行して他部署との連携をとる仕事や問い合わせが随時あるので、マルチタスクを行える能力が必要です。
しかし、目の前のオペレーターが一番大切ですのでこの点を忘れないようにしておきましょう。
問題解決力
SVには、フロントオペレーター以上の問題解決力が必要です。
エスカレーション先のSVがフロントのオペレーターより能力が劣っていた場合、顧客は不信感が大きくなるうえ、不満がクレームへと発展してしまいます。
まずは、フロント対応をしたオペレーターから状況を正確にヒアリングすること、そして、問題解決に向けて冷静に顧客と向き合い、順序立てて問題を解決へ導く能力が求められます。
なお、フロントオペレーターや顧客の意見を一方的に鵜呑みにせず、双方の意見を総合的に聴取し、冷静に問題を判断することで、問題を解決することが可能となります。
オペレーターに信頼されるマネジメント能力
職場への信頼がなければオペレーターは不満を持ち、職場を去っていきます。
SVはオペレーターにとって、応対における最後の砦です。
もし、応対に行き詰った際、エスカレーション先のSVが信頼できない人物だった場合、どうなるのでしょうか?
困難な難題を自分で抱え、相談できず、顧客の不満足やクレームに発展する可能性が考えられるのです。
SVはただ入電した呼をサポートするだけでいい、ということではありません。
しっかりとオペレーター個人のマネジメントを行って初めて、信頼されるコールセンターSV(スーパーバイザー)となりえるのです。
オペレーター以上の応対スキル
SVは、フロントオペレーター以上の応対品質が必要です。
フロントオペレーターは定期的に品質チェックを受けます。
モニタリングを行い、フィードバックを行うにあたって、もしオペレーターに劣る品質のSVから指摘を受けても、納得できないどころか反発を招く事態となるでしょう
そのためSVは自身の応対品質も日々向上させる必要があります。
例えば、話し言葉検定や応対コンクールなど、誰が見てもわかるような資格やコンテスト結果を得ることで、オペレーターに信頼されるSVとなることができます。
コールセンターSVを育成するポイント
こうした高いスキルが求められるSVですが、どういった方法で育成できるのでしょうか。
以下では3つのポイントを解説します。
育成体制の構築
「そもそもSVになる際に何か特別な研修を受けただろうか?」
このように思う方々も少なくないはずです。
SVは広範にわたるスキルが必要となる役割です。以下のポイントをふまえ研修体制を構築してみましょう。
- 明確な目的とゴールの設定
SV研修の目的とゴールを明確に定めましょう。具体的なスキルや知識、行動指針を明確にすることで、効果的な研修を実施できます。 - カリキュラムのカスタマイズ:
SVの役割や業務に合わせてカリキュラムをカスタマイズしましょう。
コミュニケーションスキル、問題解決能力、リーダーシップなどを重点的に研修することが重要です。 - 実践的なトレーニング
理論だけでなく、実践的なトレーニングを取り入れましょう。
ロールプレイやシミュレーションを通じて、実際の業務に近い状況を体験させることで、SVのスキルを向上させます。
コールセンターシステムを活用した業務効率化
SVはKPI管理やオペレーターの効率を監督する役割であり、業務を円滑に進めるためには、身体的・心理的な負担を軽減するシステム導入が重要です。
コールセンターのスーパーバイザー(SV)の業務を効率化するためにコールセンターシステムを活用する理由はいくつかあります。
- データ集計と分析の自動化
システムを用いて、オペレーターの通話回数、応答時間、問題解決率などのデータを自動的に集計・分析できます。 - トレーニングと教育の効率化
システムを用いてオペレーターの研修やトレーニングを効率的に実施できます。
このようにコールセンターシステムを活用することで、日々の身体的・心理的な負担の軽減が見込めます。
心理面でのサポート体制の構築
SVの仕事は大きな責任が伴います。
目標を達成するプレッシャーやオペレーターとの関係など、悩みはつきません。
だからこそ、新人SVがメンタルを守れるようなサポートが必要です。
ストレスや負担から離職することもあるので、相談できる場所を作ったり、定期的に業務量を見直すなど、負担を軽減するための取り組みが大切です。
コールセンターシステムのご紹介
コールセンター業務を大幅に効率化するのであれば、コールセンターシステムの導入をおすすめします。
クラウド型コールセンターシステムのパイオニアであるコラボスが提供しているコールセンターシステムは、お客様相談室や製品問い合わせセンターなどで利用されているシステムを手軽に利用できるよう、クラウドサービスという形態で提供しています。
例えば、電話システムや顧客情報管理システム、通話録音システムは効率的なコールセンター運営を行うにあたり、必須のシステムです。
コラボスのコールセンターシステムではこれらのシステムをクラウドから利用可能です。
いままで設備投資に時間や費用がかけられなかった方でも、必要な分を好きなだけ利用できるので、費用を安く抑えられます。
また、機器や設備は不要です。
さらに、常に最新の機能にバージョンアップができ、ネットワークを経由で、場所に捉われずサービスを利用することができます。
コールセンターシステムについての疑問は、コラボスまでお問い合わせください。
この記事の執筆者
コラボスブログ編集部
株式会社コラボスは、2001年に設立。現在、東京・大阪にオフィスを構えており、
960拠点以上のお客様へクラウドサービスを使ったCTIシステムを提供。
本ブログ記事サイトでは、様々なニーズを抱えたお客様のお役に立てるような情報を日々発信。
会社情報について詳しくはこちら




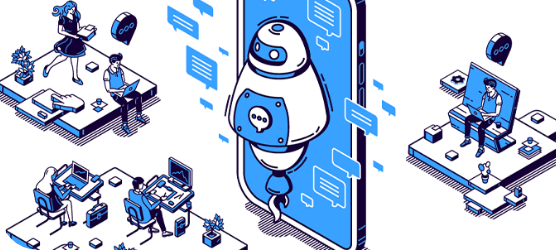

 03-6738-8707
03-6738-8707
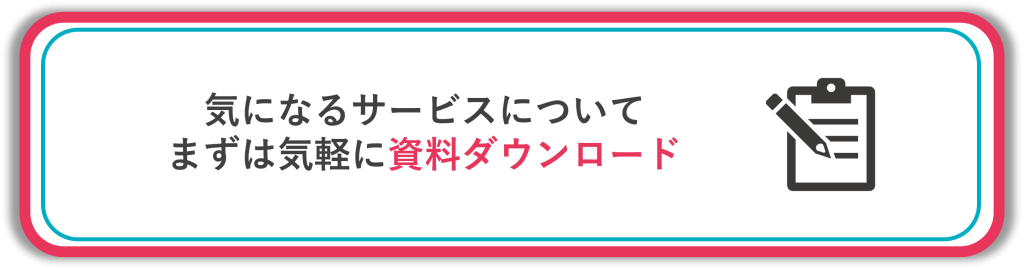
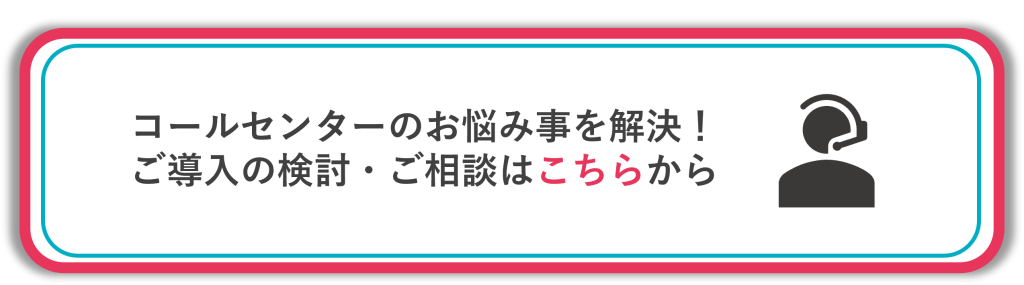
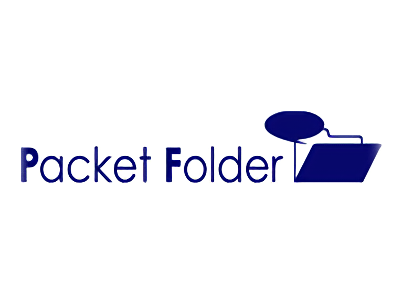


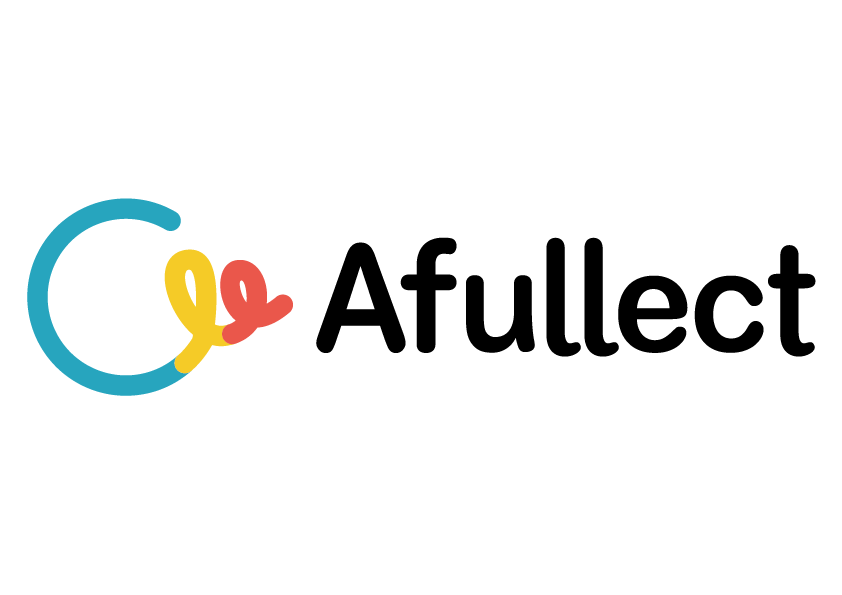
.jpg)