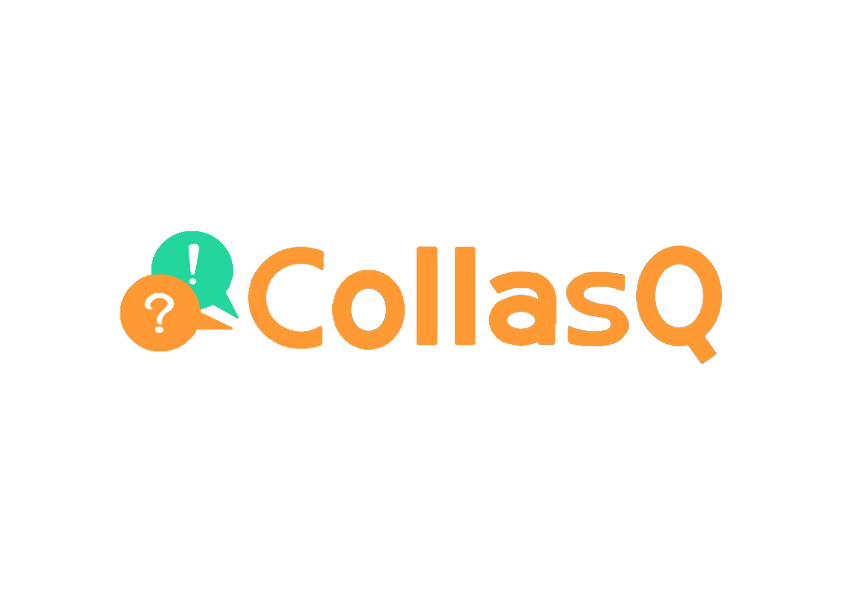総務省が自治体への導入を推進しているチャットボットって?導入事例や選び方などのまとめ

現在、少子高齢化社会が進んでいるなか、どの企業でも人手不足は叫ばれていますが、自治体でもそれは例外ではありません。
また、新型コロナウイルスが流行したことや、働き方改革の推進により自治体でもチャットボットの導入が進んでいます。
今回は、自治体に導入されているチャットボットの効果や導入事例、選び方・費用についても解説していきます。
自治体へ続々と導入されているチャットボットとは?
チャットボットとは、日本語で”おしゃべり”を意味する「チャット(chat)」と、ロボット(robot)を組み合わせた造語で、スマホやタブレットなどで文章でのやり取りができるシステムです。
地方自治体では、AIを活用したシステムを導入している106の団体の内、55団体でチャットボットが活用されていることが明らかになっています。
現在は新型コロナウイルスの影響で、なるべく非対面で問題解決ができるようにすることが求められています。働き方改革などの政策も後押しをして、チャットボットは今後続々と自治体でも導入されるでしょう。
参考:総務省公式サイト|地方自治体におけるAI・RPAの 実証実験・導入状況等調査
チャットボットを自治体に導入するメリットって?
自治体でチャットボットを導入するメリットは多岐にわたりますが、特に挙げられることの多いメリットをご紹介します。
- 24時間365日対応可能
- 人手不足の解決策になる
- 外国語でも対応できる
- 身近なスマホ・タブレットでの利用が可能
これらのメリットについて、1つずつ解説いたします。
24時間365日対応可能
チャットボットを導入すると、24時間365日いつでも対応が可能になります。地方自治体の窓口は、夕方で終わってしまったり、土日はお休みであったりすることが多いため、平日一般企業で働いている人は電話や対面での対応をしてもらうためには、有給や昼休みを活用して出向くことが多くあります。
チャットボットで解決できる内容であれば、住民の疑問もすぐに解消することができます。
人手不足の解決策になる
自治体でも人手不足は叫ばれていますが、チャットボットは人手不足の解決策として活用されることもあります。
簡単な問合せなどはチャットボットで対応することで、その分の労力を他の業務に充てることができます。自治体の長い待ち時間は住民にとってもストレスとなってしまいますが、チャットボットの活用で待ち時間が減少し、満足度の向上にも役立ちます。
また、業務効率化によって働く人の満足度も上がり、より生産性向上に役立つことも期待されます。
外国語でも対応できる
外国語を母語としている方にも対応ができることも、チャットボットのメリットです。
多言語対応したチャットボットを導入することで、電話や対面では大変な外国語での対応が簡単になります。
また、災害時に外国語での案内が少なく、日本語がまだ分からない外国籍の方が避難所にたどり着けなかったということがあり、問題視されてたことがあります。
こういったことも地方自治体が多言語型チャットボットを活用することで少なくなっていくことも期待されます。
参考:株式会社毎日新聞社|避難勧告?意味分からず 台風災害情報、戸惑う外国人
身近なスマホ・タブレットでの利用が可能
FacebookやLINEなどのSNSが社会全体に普及してきたことによって、チャットの利用に慣れている人が多くなっています。
高齢者向けのスマートフォンも普及していることがあり、文字でコミュニケーションを取り合うチャットは老若男女問わず利用される機会が増えました。
またいまや日本で多くの人が持っているとされるスマートフォンで、チャットボットを利用することにより手軽に、早く、住民と自治体を繋ぐことができ、誰でも利用しやすい状況を作ってくれます。
自治体におけるチャットボットの導入事例

チャットボットは全国各地の自治体に導入されていて、既に多くの成功事例があります。チャットボットの導入に悩んでいる自治体は、他の自治体で実際に取り組まれた導入事例を参考にしてみてください。
総合お問い合わせ窓口
自治体の総合お問い合わせ窓口には、住民から幅広い種類の問い合わせが届きます。住民からの問い合わせに対応するためには、最初に対応に適した担当者に業務を割り振らなければいけません。担当者に割り振る作業をチャットボットに任せることで、今まで担当の割り振り業務を行っていた人の手が空き、人手不足を解消できます。
証明書発行の案内
証明書発行の案内をチャットボットに任せると、営業時間外でも証明書発行に関する疑問を解決できるようになります。一般的に自治体は平日の限られた時間にしか受付していないことが多いです。
チャットボットを導入することで、住民は証明書発行に関しての疑問を簡単に確認できるようになります。平日に依頼される証明書発行の案内業務の量を減らすことが可能になります。
子育て支援
LINE公式アカウントにAIチャットボットを搭載することで、子育てをしている人に向けた発信を手軽に行えます。
自治体が企画しているイベントや制度の情報を、地域住民の該当者にLINEを通して手間なく届けられる点が魅力的です。制度について問い合わせたいのに窓口が混雑していて電話が繋がらない、という問題も解消できます。
またチャットボットは利用者の都合のいいタイミングで知りたい情報を確認できるメリットもあります。子育て中の保護者が家事の合間や子供が寝ている時など、都合のいいタイミングで活用できます。
ごみの分別
チャットボットをごみの分別に関する問い合わせの回答に対して活用すると、ごみの名前を入力するだけでごみ分別方法を教えてくれます。利用者からのメッセージが少ない場合は、質問内容について明確にするためにチャットボットが的確な質問をしてくれるのです。細かい質問への回答のような柔軟な対応もチャットボットは行えます。
自治体の観光案内・PR
チャットボットを活用して自治体の観光案内やPRを行うと、外国人から質問された場合の多言語対応に困りません。日常的に使用する簡単な英語はわかっても、相手からの質問を理解したり観光情報を案内したりするのはとても難易度が高いです。
新型コロナウイルス感染症の影響で延期をしてしまいましたが、2020年には東京五輪の開催も予定されていました。今後の訪日外国人の増加に備えて、多言語で観光情報を発信できるチャットボットを導入する自治体が増えています。
外国籍の方向けの行政サービス
観光案内と同様に、自治体には外国居住者もいます。チャットボットは対応言語を増やしていくことが可能なため、多くの外国籍の方を対象にした英語の他、中国語や韓国語など自治体に居住している人に合わせた対応が可能です。
自治体職員のヘルプデスク
住民からの問い合わせに加えて、チャットボットは社内で起こるさまざまなトラブルに対応するための自治体職員のヘルプデスクとしても活用できます。他の課からの問い合わせへの対応や、知識面でのスタッフのサポートなどの業務もチャットボットに任せることができるのです。
自治体へのチャットボット導入は総務省も推進!
現在、システムやAIなどの技術を駆使して、効果的・効率的な行政サービスを行えるように、「自治体行政スマートプロジェクト」という政策を総務省が推進しています。
その中でも、窓口受付システムや自動応答システムの関心が高く、その点でもチャットボットは注目を浴びているシステムです。
今後も自治体への導入も進んでいくことで、業務改善や人手不足解消の解決策として利用されるでしょう。
参考:総務省公式サイト|スマート自治体構築へ AI等の共同利用を支援
自治体でチャットボットを導入する際に知っておきたいシナリオ型とAI型の違い
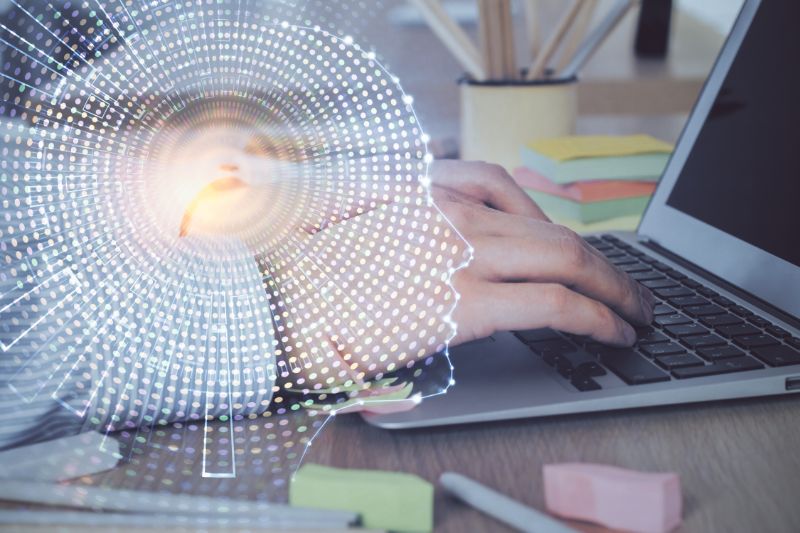
チャットボットにはシナリオ型とAI型の2種類あり、それぞれ自動応答の仕方が異なります。自治体へチャットボットを導入する前に、シナリオ型とAI型の違いやそれぞれの特徴を理解しておきましょう。
シナリオ(ルールベース)型
シナリオ(ルールベース)型のチャットボットは、予め設定してあるシナリオに基づいて回答を出すチャットボットです。
AI型よりもシンプルで、的外れな回答が少ないという点がメリットで、証明書発行の案内などで利用されていることが多い種類となっています。
AI(搭載)型
AI(搭載)型のチャットボットは、AI(人工知能)の機械学習を基に応答します。AI型のチャットボットに自動応答してもらう場合は、質問と回答を関連させたデータの取り込みが必要です。学習データが多いほど、AI型チャットボットの精度は高くなります。
自治体向けチャットボットの選び方
自治体にチャットボットを導入する際には、目的や用途に合わせてチャットボットの種類を選ぶ必要があります。最適なチャットボットを選定して、人手が必要な業務を減らし、自治体の生産性を向上させるきっかけにしてはいかがでしょうか。
シナリオ型かAI型か
チャットボットを導入する目的ごとに、シナリオ型とAI型のどちらが適しているのか異なります。
シナリオ型は、製品検索やアンケート回答など簡潔な作業への活用がおすすめです。質問内容が複雑化すると用意していた定型文で回答できなくなってしまうため、「AならB」のように答えられる業務におすすめになります。
AI型は、複雑な質問にも回答できますが、会話の精度を上げるために、データの蓄積やチューニングが必要になってきます。利用者へのおすすめ制度探しなど、多くの学習データを必要とする業務への活用がおすすめです。
SNSや他システムとの連携が可能か
自治体でSNSや他のシステムを活用しているのであれば、導入するチャットボットは他システムやSNSと連携できるタイプを選びましょう。
アプリケーション同士が連携するAPI連携機能が備わっているSNSとして、Twitter、Facebook、LINEなどが挙げられます。
スマートフォンの普及により老若男女問わず多くのSNSに触れる機会が増えたため、SNSとチャットボットを連携させることでより効率よく多くの人に情報を発信することが可能です。
有人チャット・電話対応への切り替え
チャットボットは事前に登録されていない質問の回答や、長く複雑な質問に対しては上手く対応できません。
そのため無人チャットから途中で有人チャットへの切り替えが必要になる場合もあります。
人間が質問にチャットで回答していくうちに直接会話して説明を行う必要が出た場合は、オペレータによる電話対応への切り替えが必要になることもあるのです。
基本的には無人チャットで対応し、有人対応の必要が出る可能性がある業務には対応方法の切り替えがスムーズに行えるチャットボットを導入しましょう。
自治体へのチャットボット導入費用

チャットボットは自治体の業務を手助けしてくれる便利なシステムですが、チャットボットの導入にはお金がかかります。用意できる予算でチャットボットを導入できるのか不安に感じてしまう自治体もあるでしょう。自治体へのチャットボット導入にかかるさまざまな費用について解説します。
初期費用・導入費用
チャットボットを自治体に導入する際に最初に必要となるのが初期費用・導入費用です。
チャットボットの初期費用・導入費用はチャットボットツールを提供している企業によって金額が異なります。チャットボットは導入後にも月額費用が発生するため、初期費用・導入費用が高額でも月額費用が安い場合もあるのです。
チャットボットの初期費用・導入費用の相場は、AI型が20~100万円、シナリオ型が10万円前後と言われています。
月額費用・契約費用
チャットボット導入後の月額費用に該当するのが契約費用です。月額ではなく年額で管理されている場合や、期間によって費用が変動する場合もあります。
機能や制限など選択するプランによっても契約費用の金額が変動する場合や、機能面が充実しているチャットボットの契約費用は高額になってしまう場合もあります。また、月額費用はチャットボットの使用頻度によって変動することもあるのでご注意ください。
チャットボットの月額費用の相場はAI型が10~30万円、シナリオ型が5~10万円前後と言われています。シナリオ型の中には、月額3万円程度の低価格で利用できるチャットボットもあります。
学習データ・シナリオ作成費用
シナリオ型・AI型どちらのチャットボットを選んだ場合でも、最初にチャットボットに必要なデータを学習させなければいけません。データやシナリオの作り方がわからない自治体には、作成代行を行っているサービスを利用するのがおすすめです。
しかし代行サービスを利用するとその分お金がかかってしまうため、シナリオ型のチャットボットを選択して役所内でシナリオを作成する方法もあります。
デザイン費用
デザイン性の高いチャットボットを導入したい場合には、チャットボットをカスタマイズするためのデザイン費用が必要です。自社でカスタマイズできるチャットボットもありますが、基本的にはデザイン費用を支払ってカスタマイズを依頼することが多くなります。
チャットのデザインが違うだけで利用者の使いやすさや親しみやすさに影響するため、住民に好感を持ってもらえる自治体のチャットボット作りにはデザイン費用が欠かせません。
チャットボット導入には「Challbo」が最適!
株式会社コラボスが提供している「Challbo」にはAPI連携機能を搭載していて、有人・無人チャットの切り替えが可能です。
複数サイトをまとめて対応できるマルチテナント対応機能や複数同時対応機能など、従来1つのチャットボット導入では実現できなかった機能が搭載されています。「Challbo」を導入すると複数のチャットボットを導入する必要がなく、さまざまなサイトを運営する自治体の方にはおすすめになります。
また「Challbo」は、SSL接続など個人情報を守るための仕組みは搭載され、コスト面も月額3万円で提供しています。
紹介した機能を含めた無料トライアルプランがあるため試験的な導入が可能です。
「Challbo」に興味を持っていただけましたら、ぜひ弊社までお問い合わせください。
この記事の執筆者
コラボスブログ編集部
株式会社コラボスは、2001年に設立。現在、東京・大阪にオフィスを構えており、
960拠点以上のお客様へクラウドサービスを使ったCTIシステムを提供。
本ブログ記事サイトでは、様々なニーズを抱えたお客様のお役に立てるような情報を日々発信。
会社情報について詳しくはこちら




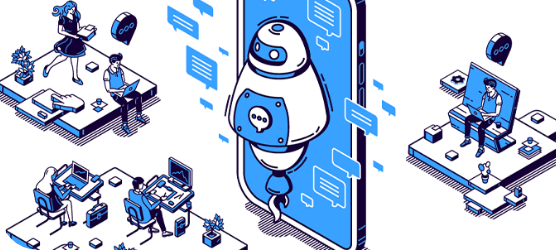

 03-6738-8707
03-6738-8707
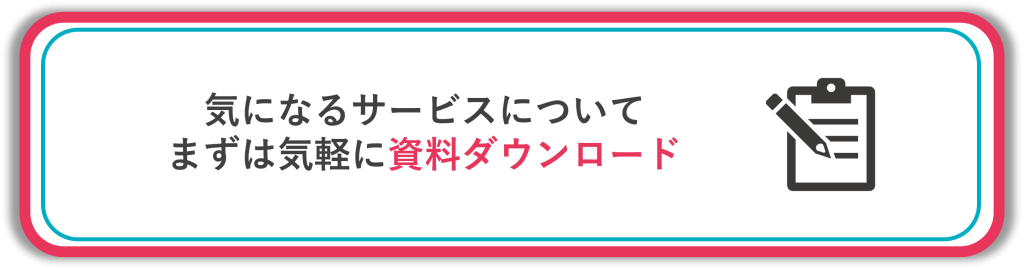
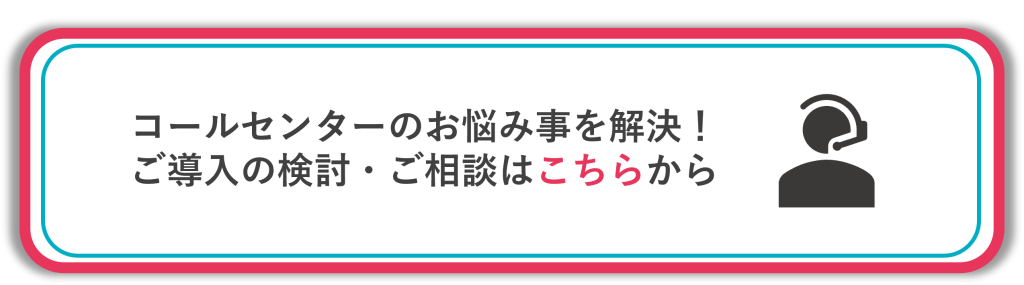








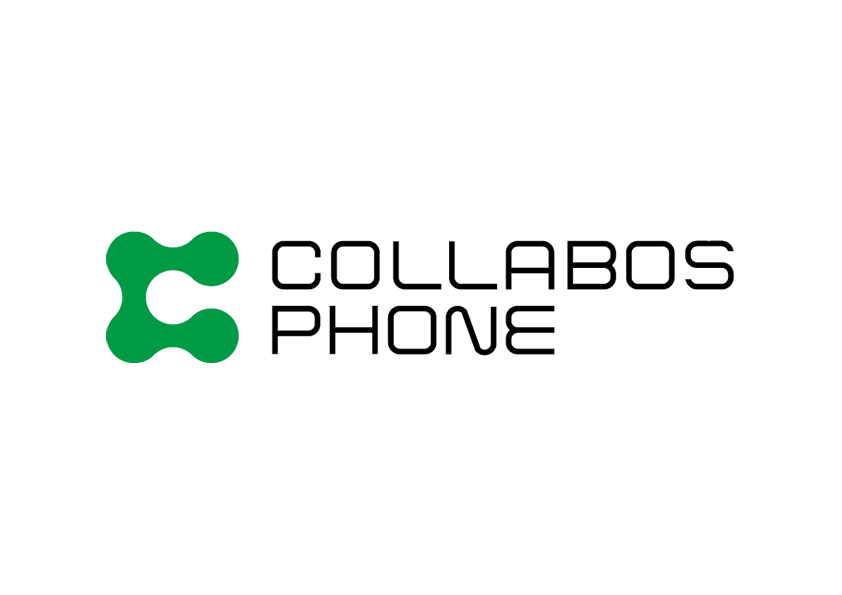



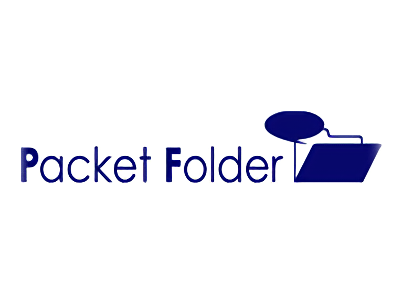


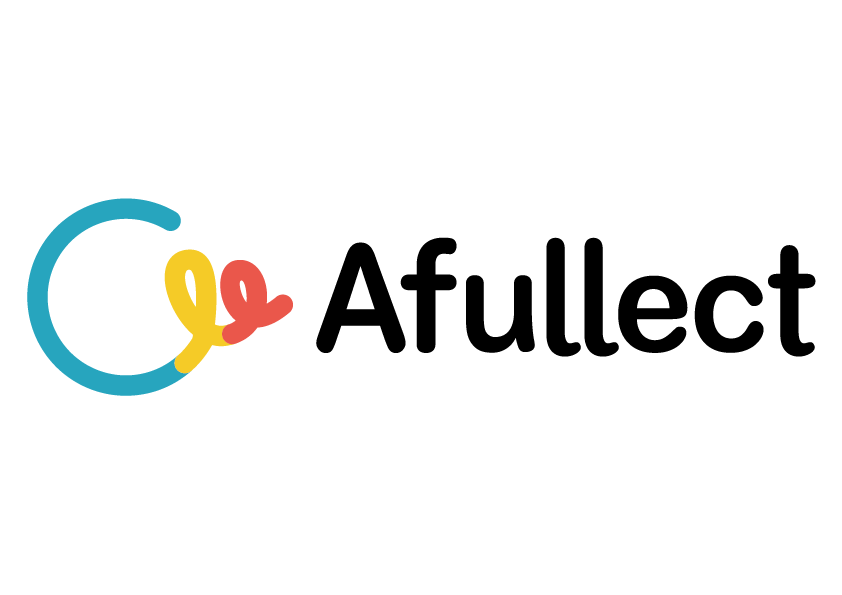
.jpg)